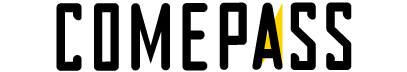2019.09.27 Fri
#Other

日本映画界、 今年最大の発見。インタビューで紐解く、話題作「メランコリック」とOne Gooseとは..
いま、とある完全自主制作の映画が注目を集めている。タイトルは『メランコリック』。ポスターからは何やら不気味なイメージが伝わってくるが、実際の物語はというと、東大を出たもののパッとしない生活を送っている主人公の若者が銭湯でアルバイトを始めたところ、そこで夜な夜な行われていた殺人処理に巻きこまれる ——という、かなりぶっ飛んだ恐ろしいものだ。だが語り口は意外にもコミカル。主人公の恋愛や仕事の模様を交えながら、アクション、サスペンス、青春劇と様々な要素を軽やかに渡り歩いていく。
このフレッシュで独創的な作品の制作の中心となったのは、1987年生まれの青年3人である。監督・脚本・編集を務めた田中征爾、映画内で絶大な存在感を見せるばかりかアクション俳優としても活躍する磯崎義知、そして、制作のきっかけを作った主演兼プロデューサー皆川暢二。彼らは映像製作ユニット〈One Goose〉を立ち上げ、完全なインディペンデントでひとつの作品を作り上げた。多額の金がなくても、有名でなくても、面白いものを作ることはできる ——『メランコリック』は、その気持ちの良い実例として僕たちに勇気をくれる映画でもある。
関西での上映開始に合わせて、はじめに声を上げた皆川暢二に話を聞いた。映画ではボンクラ風情の主人公・和彦を見事に体現していた彼だが、実際に会ってみると、驚くほど爽やかで意志の強い若者がそこにいた。
Text / Tsuyoshi Kizu
ダークホース的な位置づけ
——東京ではもう上映されていますが、反響はいかがですか?
皆川:東京では自分たちが思っていた以上のお客さんが来てくれて、『メランコリック』という作品が映画好きの間でかなり広まってくれているので、いい意味で驚いています。
——そのなかでも面白かったリアクションはありましたか?
皆川:このポスターやチラシのイメージで、先入観からかスプラッター映画と思っていたひとが多いみたいで。そのせいで、「いい意味で裏切られた」という反応がすごくありますね。それは良かったなと。一般のお客さんが来るまでは正直読めないので… 映画祭では映画業界のひとたちは観ますけど、あくまでそれは特殊なものなので。だから一般でも受け入れられてホッとしましたね。
——タイトルもそうですけど、一見、何の映画かわからない部分もありますからね。ちょっと得体がしれないというか(笑)。
皆川:そうですね(笑)。これは東京国際映画祭で上映されたんですけど、なぜかチケットがすぐ完売したんですよ。有名な俳優も出ていない、監督も新人、何の話かもよくわからないっていう(笑)、ダークホース的な位置づけだったのかもしれません。得体のしれなさがキャッチーだったのかもしれないですね。

映画「メランコリック」より
バンドのようなチーム
——ではそんな作品についても伺いたいのですが、まず本作制作のために立ち上げた映像製作チーム〈One Goose〉についてお聞かせください。そもそもどういった経緯でできたものなのでしょうか。
皆川:この映画に関しては、自分が「作ろう」と言い出したんですよ。で、そこからどうするかとなったときに… まず監督の田中征爾ですが、自分が舞台をやっていたときにある演出家に演出助手として呼ばれたんですよ。その演出家が大学で講師もやっているひとで、田中くんがその教え子だったみたいで、彼も呼ばれていて。彼と出会ったのはそこですね。8年前ぐらいです。田中くんには、映画の見方の切り口や、お芝居をしている先輩にも物怖じしない姿勢に驚かされました。同年代の人間で、みんなが納得するような的確な知識を持っている人間が自分の周りにはいなくて、そのときから「すごいな」という認識がすごくあった。
——なるほど。
皆川:もうひとり、金髪の殺し屋を『メランコリック』で演じている磯崎は、彼が主演していた短編アクション映画に役者として自分が呼ばれたのがはじめですね。ふたりとはそういう形で出会って。磯崎くんも映画を観る独自の視点を持っているし、俳優としても見ているポイントがひとと違うし。ふたりに関しては、本当にリスペクトが根本にありますね。
——それで声をかけてチームを組んだのですね。企画としては、『メランコリック』単発の予定だったんですか?
皆川:もともとは、この3人でやるにしてもユニットを組まないと周りもわかりづらいし、っていうぐらいのところで。基本は『メランコリック』だけのためのものでしたね。ただその後、それがしっかりした形になって、今後もやれるんじゃないかなという自信にもなったので、これからも〈One Goose〉っていうユニットで映画を作りたいなと思っています。
——変な話ですけど、バンドを組むようなイメージではなかったですか?
皆川:あ、でもそうだと思います。あとになって思ったんですけど、こういうスタンスってあまりないので。
——珍しいですよね。
皆川:そこは自分たちでもあとで再認識して、面白いと思ったところですね。
——そういう意味では、世代が同じだというのも大きかったんですか?
皆川:みんな同年代ですからね。そこは大きいですね。自分がプロデューサーで、監督がいて、あとアクション構成も兼任できる俳優がいて……という形なんですけど、そこが全部横一線でできるので。変な縦の関係がなくて、「純粋にいいものを作っていこう」というところで話し合えるし、3人それぞれのいいところを出し合っていける。そういうところはこの作品に反映されているのではないかな、と。
——結成されたときの決めごとはあったんですか?
皆川:いや、決めごとはなかったです。テーマもそこまで決めてなかったんです。3人それぞれが映画を観て得た知識と、「いいものを作ろう」という純粋な想いだけでしたね。そのオリジナリティを出せるのがインディーズの強みなので、そこはすごく意識していました。「誰も見たことがないものを作ろう」という想いは共通して持っていたと思います。

同い年の3人で構成される映像製作チーム『One Goose』。左から皆川暢二、田中征爾、磯崎義知
光の当たらないところ
——そこから制作はどのように進んでいったのでしょうか。
皆川:3人で企画やアイデアを考えて、こういった形で進もうとなった段階で田中監督が脚本を仕上げるという流れですね。
——ストーリーも3人で相談し合って作っていく感じだったんですか?
皆川:そうです。で、銭湯をメインのロケ地にしようと言ったのは磯崎くんです。最初は採石場とかを考えていたんですが、正直予算の問題もあって。あと、銭湯であればストーリーがすべて一貫して作れる。それに海外に出したいというのもあって、銭湯というのはその意味でキャッチーさもあるのかなと。それでドンピシャだと思って即決しました。
——それにしても、その銭湯で殺人処理が行われているという発想がすごい(笑)。それはどこから出てきたものだったんですか?
皆川:殺人処理に関しては――『ジョン・ウィック』とかで、殺人のあとに綺麗に掃除するひとっているじゃないですか。でも、ああいうひとにあまり光は当たらない。だから当ててみたら面白いんじゃないかと。
——なるほど、それが綺麗に銭湯という舞台と結びついたと。あと、監督が海外ドラマの『ブレイキング・バッド』の影響を受けたというのを読んだのですが、具体的にはどういった部分だったのでしょうか。
皆川:まずはバディものというのがひとつ。あと、主人公がもともと化学の先生だったのが、どんどん泥沼にはまっていくというか。しかも、裏の世界で認められていくことで自尊心を獲得していく。そういうところの着想は確実に影響を受けていますね。

映画「メランコリック」より
——『メランコリック』って突飛な話なのに、多くのひとが入りやすかったり共感しやすかったりする映画にだと思うんです。いい意味で庶民感があるというか……僕はこれ、ひとつには労働の話だと思っていて。
皆川:ああ、お仕事ムービー。
——上司に認められたいとか(笑)。社会から取り残されたひとが、労働することで自尊心を得るという。下町が舞台というのもありますし、普通のひとを描きたいというのはあったんですか?
皆川:いや、下町を描きたいというのはなくて。まず、田中くんが作る物語の主人公って大体こういう感じなんですよ。彼はカッコいい人物を描くのが苦手。そういうひとを描くとなんか照れくさくなるみたいで。彼が描く主人公は欠点があって、わかりやすく人間っぽいというか。
——そういった人物を演じる上で、皆川さんはどういった部分を意識しましたか?
皆川:僕はこういう役をやったことがなかったので、内面というより動きから入りました。映画内で見られるような、特徴的な動きを馴染ませるところから始めましたね。あと東大にも行きましたし。それに過去に身近でいた存在の記憶なんかを集めてますね。
——東大に行ったっていうのは学生の顔や動きの観察のためですか?
皆川:そうそう。やっぱいろんなひとがいる。ただ、あとで思ったのは、東大だからってピッタリのひとがいるわけではなくて、いろいろなひとのパーツを集めてきて馴染ませたところがありますね。
——属性に縛られるものではない、という。僕は『メランコリック』は若いひとにもぜひ観てほしいと思っているのですが、皆川さんはこの作品のどういったところを見てほしいと考えていますか?
皆川:「なんで自分の環境ってこんなのなんだろう」って思うことってあるじゃないですか。でも、映画のなかで松本がうどん食ったあとに「和彦さんの家族ってあったかいっすね」って言う。そこではじめて、和彦は自分の環境を他者の視点で意識する。「自分の環境って捨てたもんじゃないんだ」と。楽しいことって本当に些細なとこにもあるし。そういったところを感じてもらえたらなと思います。

自分たちの手で作ること
——皆川さんはプロデューサーでもあるわけですけど、プロデューサーとしてはこの映画をどんな風に捉えていますか。
皆川:じつはそれまで田中くんの映画を1本しか観たことがなくて。それでなんで声かけたんだって話ですけど(笑)、自分は直感を信じる人間なので。で、脚本をもらった段階ではわからないことが多々あったんですが、本読みをやったときにわかってきて、「これはいける」と思いました。
——ほかのキャストの配役なんかも皆川さんが中心にされたんですか?
皆川:はい、自分が中心に候補を挙げて3人で決定するという流れでした。東役の羽田真さん、アンジェラ役のステファニーはキャスティング協力で入って頂いたEIJI LEON LEEさんの協力で決定しました。その他のキャストは一緒に舞台を行った仲間、先輩などをメインにお声掛けさせて頂きました。
——そういったところも含めて、本当にインディペンデントというか、自主制作映画ですよね。さぞかしプロデューサーが大変だったと思うんですけど(笑)。それゆえの苦労はありましたか。
皆川:まずはお金の部分ですよね。過去に何の実績もないので、簡単にお金は出してもらえないし。で、「お金の部分は俺が何とかするから」という言い方をしちゃったんで、やるしかないなと(笑)。
——すごい(笑)。
皆川:あと、みんなが近しい人間だからこそ、チームをまとめるバランスが難しいんですよ。撮影現場なんかでも、仲の良さからダレる方向に行きかねない部分もある。ただそこはみんなわかってくれて、「やるときはやりましょう」という空気は作れました。
——そういった空気は作品からも伝わってきました。では最後に、〈One Goose〉の今後の展望についてお聞かせいただけますか。
皆川:次回作の企画は出しているんですが、やるのであれば、日本国内のインディーズ作品というよりも、海外を絡めてやりたいと思っています。ロケ地を半分海外、半分日本にするとか。小規模の制作でそういうところにトライしているものってあまり知らないので。やる度にハードルを上げていきたいというのもあるし、それをしないとチームとして衰退していく危機感もある。そういった意味で、海外はチャレンジとしてやりたいですね。
——おお、本当にバンドのセカンド・アルバムみたいな(笑)。過去の成功例とは違うことをやるぞという。
皆川:そうですね(笑)。そのほうがモチベーション上がりますからね。

皆川暢二
1987年10月23日生まれ。神奈川県出身。
高校卒業後、体育教師を目指し大学に進学したものの、ひょんなきっかけで俳優の道を志す。 小劇場を中心に活動していたが日本に居辛さを感じた為、ワーキングホリデーを活用しカナダに。 帰国後は映像作品を中心に俳優業を再開したが、自身の手で映画を作りたいという思いが強くなりOne Gooseを発起。2018年映画『メランコリック』を主演兼プロデューサーという形で制作。 俳優 / プロデューサー / 旅人という様々な草鞋を履きながら既存の映画・俳優の在り方とは違う、新たな道筋を作りたいとチャレンジ中。

メランコリック
監督・脚本・編集:田中征爾
出演:皆川暢二 / 磯崎義知 / 吉田芽吹 / 羽田真 / 矢田政伸 / 浜谷康幸 / ステファニー・アリエン / 大久保裕太 / 山下ケイジ / 新海ひろ子 / 蒲地貴範ほか
制作:One Goose
映画公式サイト
TAG
おすすめの記事
-
初のオンライン開催!! 街の眼10年史を語る《カジカジ座談会 : 前編》をどうぞ 初のオンライン開催!! 街の眼10年史を語る《カ...
2020.06.13 Sat#Osaka
-
『カジカジ』のイベント限定商品が買えるオンラインストアがオープン!! 『カジカジ』のイベント限定商品が買えるオンラインス...
2020.05.02 Sat#Kansai
-
カジカジ編集部が行く!いけてんの!? 徳島ツアー ~前編~ カジカジ編集部が行く!いけてんの!? 徳島ツアー ...
2016.07.23 Sat#Other